前にもどる
表紙にもどる
次に進む

第一回 紅茶とのヒサンな出会い
こんにちは。あうくだの母です。なんとエッセイなるものを書くことになりました。これはすべて、あうくだの父(以下、父と記す)の陰謀です。

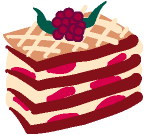
 父のシュミで始まった「大瀧新聞」も通算30号。あれよあれよというまにコーナー数は増え、当初「表紙だけ描いてくれたらいいから」と言われていた私の負担は雪だるま式に膨れ上がっておりました。まあ、文章を書くのもマンガを描くのも好きなので、発表の場を与えられて、舞い上がっていた感もなきにしもあらず、なんですが。
父のシュミで始まった「大瀧新聞」も通算30号。あれよあれよというまにコーナー数は増え、当初「表紙だけ描いてくれたらいいから」と言われていた私の負担は雪だるま式に膨れ上がっておりました。まあ、文章を書くのもマンガを描くのも好きなので、発表の場を与えられて、舞い上がっていた感もなきにしもあらず、なんですが。
それにしても、毎月更新を原則とする「大瀧新聞」に、表紙、4コマまんが、小説、挿絵、料理、ニュース記事を提供していくのはけっこう大変で、とうとう料理コーナーを打ち切ることにしたのです。ネタも尽きたし。
やれやれ、ちょっとラクになるなー、と思っていたら、父の逆襲です。
「新しいコーナー、紅茶のエッセイにするからね」……おいおい、だれがそんなもん始めるって言ったー???
「紅茶、好きでしょ。エッセイ書きたいって言ってたでしょ」
言いました。はい。でも「エッセイは読むのは簡単だけど、書くのは思いっきり難しいねー」とも言ったはずなのに……。
いろいろ反論しましたが、結局、このコーナーを始めることになりました。
紅茶大好き人間の私ですが、専門家ではないので、むずかしいことは書けません。昔の友達に久しぶりに会って、お茶を飲みながら世間話でもしているつもりで、おつきあいくださいね。

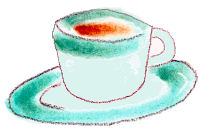
 前振りが長くなってしまいましたが。気をとりなおして、「TEA ROOMへようこそ」記念すべき第一回は、私と紅茶との出会い、です。
前振りが長くなってしまいましたが。気をとりなおして、「TEA ROOMへようこそ」記念すべき第一回は、私と紅茶との出会い、です。
これがなんとも笑っちゃうくらいヒサンでねー。よく紅茶嫌いにならなかったもんだと思います。だってどんなものでも、最初に食したときの印象って大きいでしょ。とくに、ものごころつくかつかないかのころって、なんでもインパクト強いし。
私が最初に「紅茶」を飲んだのは5歳のとき。同居していた父方の祖母に出してもらったのですが、これがなんと、コーヒーかと思うぐらい、真っ黒な代物でした。
当時、祖母は冬になると部屋に火鉢を持ち込んで、お湯をわかしたり、パンや餅などを焼いたりしていました。明治生まれの祖母は、いただきものの缶入りの紅茶を煎じ薬と勘違いしていて、土瓶に入れて煮出して飲んでいたのです。
それがどうやら、のどの痛みや寒気などの風邪の症状を緩和させるのに効いたらしく(あくまでも祖母の言)、私が咳をしていたときに「これをお飲み。『べにちゃ』というてな、かぜによう効くから」と出してくれたのでした。
「べにちゃ」はどす黒く、こげくさいにおいがしていました。しかし祖母が私のためにいれてくれたのです。私はいわゆる「外面のいい子」でしたから、祖母のご機嫌を損ねてはいけないと、思い切ってそれを飲みました。
味は、不味い、の一言に尽きました。さびたような、舌がしびれるような、変な感覚でした。そのうえ私がまだ子供だったからでしょうか。祖母が砂糖を山盛り3杯も入れていたので、えぐいことこのうえない。
これを読んでいる皆様の中には、それまでふつうの紅茶を飲んだことがなかったのかと言う方もおられるでしょうが、私の両親は日本茶一筋、コーヒーや紅茶といった「ハイカラ」なものには一切縁のない、田舎の人間でした。半径1キロメートル以内に民家のないド田舎で、そういう両親に育てられたのです。家にある飲み物といったら、日本茶と牛乳と、晩酌用のお酒だけ。

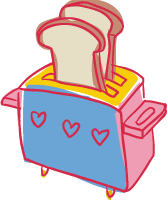
 こういうわけで、その後、本当の(?)紅茶を飲んだときの感激は、言葉にすることができません。
こういうわけで、その後、本当の(?)紅茶を飲んだときの感激は、言葉にすることができません。
小学校に入ってから、友達の家で出してもらったのは、レモンティーでした。きれいなオレンジ色の、心地よい香りのその飲み物は、どう考えても祖母がいれてくれたものとは別ものでした。
ま、そりゃそうだわな。ばーちゃんが出してくれたのは「べにちゃ」だもんなあ……。いまになれば、なつかしい思い出です。
記念すべきエッセイ第一回は、文体めちゃくちゃ、内容がないような、今後が多分に危ぶまれるものとなってしまいました。
次回はもう少しまともなものが書けるかなあ。
私にエッセイを書かせたことを後悔してる父のじたんだ踏む音が聞こえます。へへへ。
ではまた、お目にかかりましょう。 (つづく)

1998年12月号
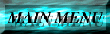




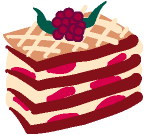
 父のシュミで始まった「大瀧新聞」も通算30号。あれよあれよというまにコーナー数は増え、当初「表紙だけ描いてくれたらいいから」と言われていた私の負担は雪だるま式に膨れ上がっておりました。まあ、文章を書くのもマンガを描くのも好きなので、発表の場を与えられて、舞い上がっていた感もなきにしもあらず、なんですが。
父のシュミで始まった「大瀧新聞」も通算30号。あれよあれよというまにコーナー数は増え、当初「表紙だけ描いてくれたらいいから」と言われていた私の負担は雪だるま式に膨れ上がっておりました。まあ、文章を書くのもマンガを描くのも好きなので、発表の場を与えられて、舞い上がっていた感もなきにしもあらず、なんですが。
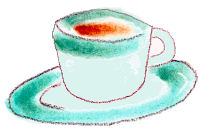
 前振りが長くなってしまいましたが。気をとりなおして、「TEA ROOMへようこそ」記念すべき第一回は、私と紅茶との出会い、です。
前振りが長くなってしまいましたが。気をとりなおして、「TEA ROOMへようこそ」記念すべき第一回は、私と紅茶との出会い、です。
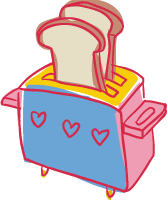
 こういうわけで、その後、本当の(?)紅茶を飲んだときの感激は、言葉にすることができません。
こういうわけで、その後、本当の(?)紅茶を飲んだときの感激は、言葉にすることができません。